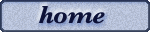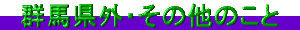登山日2025年3月24日

大塚山山頂
|
先月、御岳山から大岳山を歩いたときに、御嶽山神社に到着した時間が早かったためか、旧本殿に向かう門が閉じられていた。そのために御岳山山頂の標識を確認することができなかった。ちょっと不完全燃焼ということもあり確認のために再登することにした。これだけではもったいないので近くにある日の出山と大塚山も登ろうと計画した。 3月24日(月) 御岳山ケーブルカーの滝本駅駐車場に到着したのは午前7時だった。しかし、駐車場のゲートは閉じられたままで係員も見当たらない。すでに数台が門の前に並んで開くのを待っていた。7時10分頃やっと係員が現れて、慌てる様子もなくゲートの前にあるトラテープを取り外した。始発まではあと20分ほどなので支度は急がなくてはならない。なんとか支度を整えてケーブルカーの始発には間に合わせることができた。乗客は10人ほどなので一ヶ月前よりも乗客は増えた感じだ。 終点の御嶽山駅に降り、周囲を見渡すと始発ということもあり、広場(御岳平)は閑散としていた。迷うこともなく、鳥居をくぐり日の出山に向かって遊歩道を進んでいく。いつもながら御師集落は迷路のようであり道幅も狭い。神代ケヤキのところで道が分岐するので左の道に入る。しかし、標識が少なくよくわからないので適当に進んでいく。やがてはっきりとした道に合流し、そのまま導かれるように前に進んでいく。植林の中の道はよく踏まれており間違うことはない。 鳥居をくぐると階段の道となり、歩幅の合わない段を苦労しながら歩いていく。周囲は杉立に囲まれて展望はない。今日は曇り空で風が吹くと身震いするほどの寒さだった。幅の広い階段の道を上りあげると建物が見えてきた。建物の前は広場のようになっておりベンチが数脚置いてあった。建物はトイレだったが今は使えないようでトラテープが張ってある。その入口にはステンレス製の便器がうず高く積まれていた。その便器はステンレス特有の光沢が妙に違和感を持って見えた。さらにここには東雲山荘という山小屋があり宿泊もできるようだが、あいにくとオフシーズンのようだった。ここからも階段を登り上部に登っていく。このあたりは公園整備を行ったのであろう、石積の痕跡があり城趾のようでもあった。上りあげると山頂に到着するが、いかにも都会の山といった感じだ。東屋があり周囲にはベンチがいくつも置かれている。東屋にはライブカメラが設置されていたが、運用はされていないようだった。誰もいない山頂でベンチに腰掛けてゆっくりと白湯を呑んだ。日の出山で休憩後、往路を戻ることにする。
武蔵御嶽神社前の土産物屋で日の出山の山バッジを見つけたので購入。店の人がお茶をいれてくれたので世間話をしながら美味しくいただいた。店を出て神社の手水舎の柄杓で水を汲もうとしたら、後ろの方で女性の声がする。みれば私を追いかけてきたのだが、手にはストックを持っている。そうだ、世間話に夢中になりストックを置き忘れてしまったのだ。ありがたく礼を述べてその親切さに感謝した。神社前の階段は下手な山登りよりもきついとおもう。やっとの思いで拝殿までたどり着き、その後ろを見ると旧本殿の扉が開いているのを確認した。これで目標が達成できたと思いその中に入った。その奥まったところに「御岳山山頂」と書いた標柱があった。さらにその先には奥の院遥拝所があり、ここから見ると三角錐の奥ノ院峰を間近に見ることができた。奥ノ院峰の山頂からは高度感を感じなかったが、ここから見ると恐ろしいほど屹立したその峰はとても立派に見えた。拝殿に戻りお参りしてから、前回行けなかった長尾平に行ってみることにした。 参道の階段途中から下に降りて長尾平に向かう。この付近は名前の通り平坦で気持ちの良いところだ。ここにはトイレも有り、ヘリポートも完備されていた。さらにその奥には東屋があり、ここからはさきほど登った日の出山が大きく見えていた。ここでゆっくりしたかったがもう一山登りたいところがあるので、早々に引き上げることにした。
これまた前回行けなかったビジターセンターに寄ってみることにした。ところがなんとこの日は休館日なので、またもや入館することができなかった。しかたなくこのまま大塚山を目 指すことにする。富士峰園地の巻き道を通り進んでいく。6本の道が交わる広場に出ると標識があり行くべき方向がわかった。この付近明るい雑木林で気持ちがいい。広い道を進んでいくと程なく大塚山の山頂に到着。大きな山頂標識と三角点がそこにはあった。また近くには大きな鉄塔があり、しずかな山頂にはちょっと合わないなあと感じた。ここにもテーブルと椅子がありこれも都会の山といった感じがする。 大塚山を辞して斜面を下ると立派な休憩棟がある。推測だがこのあたりにキャンプ場がありそれの遺構なのかもしれない。しかし、水がなければ野営も成り立たないと思うがどうだろう。ここから中ノ棒山(中塚山)に向かう。ほぼ平坦な道となっているが、気になるのは枯れ葉のついた枝が散乱していることだ。木の幹には鋭い爪痕が残っている。これはあいつがいるのは間違いなさそうだ。ビクビクしながらちょっぴり早足で先に進む。中ノ棒山はピークというものではなく、登山道の通過場所そのものだった。小さな山頂標識がなければ気が付かないような場所で、展望は全く優れていなかった。 中ノ棒山からは大塚山の巻き道を辿って戻ることにする。この道は重機あるいは軽トラックが利用するのだろうか。タイヤの轍が残っている道だった。その途中に墓地があり、お彼岸が近かったため生花がまだまだ鮮やかな色を保っていた。その横に道があり高みを目指すと東屋があり手製の山頂標識が立木に取り付けられていた。展望もなく留まる理由もないのでそのまま林道に降り立った。
降りたところは往路に通過した6本の道が交わる広場だった。ここから網のゲートを開けて富士峰園地に向かう。ここも階段があり老体にはちょっと堪える。この付近、蕾こそ見えないがカタクリの葉がかなり見られた。山頂には神社があったがオフシーズンは訪れる人も少ないようでひっそりとしていた。更に進むと再び網のゲートが有りそこを開けるとリフトの山頂駅があった。これもオフシーズンで閑散としている。むささびブランコが設置してあるがシートに覆われていた。ここからの展望は晴れていれば素晴らしいのだろうが、今日は生憎の曇天で霞む風景が見えているだけだ。この場所のすぐ下には畑があり、男性が一人畑作業に精を出していた。ここで農作業をやるのはちょっと勇気があるなあと思う。再びゲートを開けて下山することにする。到着したのはケーブルカーの御嶽山駅の広場だった。ちょっとだけ休憩して再び鳥居を潜ってビジターセンター方面に行く。 今日の下山はケーブルカーを使わずに林道を辿ることにしている。この林道は御岳山に住む人達の生活道路なのだろう細いながら舗装され整備が行き届いている。それにしても急勾配で細くすれ違いは不可能だ。おまけにクネクネと曲がりくねっているものだから気を許すことはできない。周囲は杉の巨木に囲まれて陽の光は届かない。降雪があった場合はとても素人には通行するなど考えられないだろう。あまりの急傾斜の道なのでつま先が痛くなる。途中でケーブルカーの高架の下を潜る場所があり、ここで運良くケーブルカーの通過するところを見ることができた。このあたりで林道の約半分ほどだろうか。素直にケーブルカーを使えばよかったとちょっと後悔した。結局は林道を40分近くかかって滝本駅まで歩ききった。
07:30滝本駅====07:39御嶽山駅--(1.10)--08:46日の出山09:13--(.59)--10:12御岳山神社10:22--(.18)--10:40長尾平10:57--(.14)--11:11ビジターセンター--(.34)--11:45大塚山12:03--(.10)--12:13中ノ棒山--(.19)--12:32円塚山--(.11)--12:43富士峰園地--(.09)--12:52御岳平--(.08)--13:00分岐--(.38)--13:38滝本駅 群馬山岳移動通信/2025 |