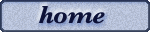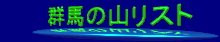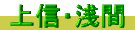消された山名のある「竜ヶ岳」
登山日1993年11月6日

「竜ヶ岳」は国土地理院の地形図には標高1410.5mの記載があるだけで名前は記載されていない。従っていろいろな地図にも記載されたものを見る事はない。もちろん「コンサイス日本山名辞典」にも出てこない。唯一、ガイドブック「群馬の山歩き130選」でその名前を見るだけだ。以前から気になっていた山だったが、その機会がなくてなかなか登る事が出来ない山だった。木の葉が散ったこの時期にやっとその機会を作る事が出来た。
11月6日(土)
県道長野原倉渕線を二度上峠に向かって行くと右側に「天然記念物ヒカリゴケ洞窟4.6km]の立派な標識がある。この標識に従って右に曲がるとすぐに舗装路は終わりダートに変わる。そして民家を通り抜けると林道のゲートにたどり着く。ゲートは閉じられたまま鍵もしっかりかけてある。何か文字が書いてあるのだが錆がひどく読み取れないのでゲートの左を通り抜けてミニバイクでそのまま進む。
林道はダートでミニバイクでは砂利が多すぎて走りにくい、むしろ4輪車のほうが走りやすいだろう。
林道のゲートから登山口まで約4kmあった。歩くとなると片道最低30分はかかるであろう。登山口には「ヒカリゴケ洞窟880m」の標識がある。(この880mは洞窟まで880mなのか標高880mなのか解らない)。高度計をここで880mに合わせておいたら山頂でほぼ正確な数値を示した)標識の手前には林業関係の作業小屋があり、道幅が広くなっていたのでここにミニバイクを止めて歩き始める。
登山道は始めは電柱の廃材を利用した丸太で作った階段が設置されており、いかにもハイキングコースの様な趣がある。植林された桧の中を道を過ぎると薮の多い道に入り、小さな沢を渡ると再び「洞窟へ250m」のこれ又立派な標識が現れる。
「群馬県天然記念物・笹塒山のヒカリゴケ/ウサギコウモリ生息洞窟」は登山道の右上にある。頑丈な鉄の檻が洞窟の周りに設置してあり、鍵もかかっていた。洞窟の中を見ると季節外れにもかかわらず穴の奥左側に、エメラルドグリーンの苔が光っているのが見えた。写真を撮ったがおそらく写ってはいまい。コウモリも居るのかなと思い穴に向かって手を叩いたが何も変化は無かった。
再び登山道に戻りここから数10m程沢の中を歩く。沢は水もなく石がゴロゴロしているだけだ。ほどなく小さなケルンが積んである場所に着く。これを目印に右に折れて尾根道に入る。
紅葉もこの標高1000m付近が限界で、ここから先は落葉した木々の中の道を登る事になる。落ち葉を踏む音が静寂に包まれた山の中に響きわたる。
道は十八曲がりの道にはいる。ただひたすら右へ行ったり左へ行ったりジグザグに道は続いている。本当に18回も曲がるのだろうか。心配になって山の斜面の上を見ると、何となく道らしきものが上に向かって続いているので、18回以上曲がる様な感じである。このジグザグの道は嫌だからと言って直登するには傾斜がきつくて不可能だ。時々木の間から山頂が見え隠れしている。ここから見るとかなり立派な山に見える。しかしこの道は夏には登れるのだろうか。葉が茂る季節は枝が道を塞ぎ展望はないし、単調な登りはかなりきつい事だろう。
標高1200m付近で左に下る道があるが、ここは右に行く。少し歩くと今度はそのまま真っ直ぐに進む道と、左に折れて登る道が現れる。ここは左に進む。十八曲がりの道は妙な分かれ道が出てきても上部に向かって進む事が正式のルートである。
標高1275m付近。落ち葉がガサガサと動いた。良くみるとヤマカカシが赤い腹を見せて動いている。思わず立ち止まってしまった。腕捲くりした腕を見ると鳥肌が立っている。私はヘビとイモムシと女性に滅法弱い。思わず後へ下がった。ヤマカカシは寒いためかゆっくりと穴の中に消えていった。ここはもう歩く気がしない。この道は先には進まずに山の斜面を直登した。
十八曲がりの道の上部の方は胸のあたりまである笹薮のヤブ漕ぎとなった。先ほどのヤマカカシの件があったのでヤブ漕ぎはどうも気持ちが悪い。掴む木の枝がなにかいやな感じがする。笹薮を抜ける為に喘ぎながら早歩きして、4分程で薮道をクリアーした。
薮道を抜けると植林標柱が有ったのでここで8分ほど休んで気分を落ちつかせた。植林標柱には「カラマツ・1050本」の文字が読める。ここから道は左に続いているがガイドブックによると、このまま直登した方が薮が無くて簡単に登れるとあるのでその通りにする。たしかに薮漕ぎにはならないがかなりの急登だ。汗が一気に出てくる。
稜線には微かな踏み跡がある。ここは帰りの時に稜線から外れて下に降りる地点がわかりにくい。メモ用に持ってきたA4のコピー用紙を木の枝に刺しておいた。
踏み跡を頼りに忠実に稜線を歩くとやがて「竜ヶ岳」山頂に着く事が出来た。登山開始より1時間24分だった。
三等三角点のある山頂は雑木に覆われて展望は余り無い。かろうじて鼻曲山/剣の峰/角落山の稜線方向が開けている。あとは木々の間から浅間隠山が望める程度だ。山頂には石の祠があるが無惨にも倒木が上に乗っており、ちょっと位置が台座よりずれている感じだ。
気になったのは山頂標識が明らかに人の手によって壊されていたことである。拾い集めてみると2枚になった。文字はどちらも「岩岳/1410.5m」とある。たしかにガイドブックには「竜ヶ岳(岩岳)」と書いてある。竜ヶ岳の山頂標識はそのまま残っているところを見ると誰かが山名を統一しようとしてやった事なのだろうか。私には解らないが山の名前はそれぞれ歴史が有る訳なので、こんな形で一つの山名を消そうとしているのだとしたら納得行かない。
山頂では利根郡笠ヶ岳移動のFAT/野田さんとQSOする事が出来た。野田さんとは足尾山魂の庚申山での新年会でお会いした事はあるがQSOは初めてだった。しかし、どうしても無線機から聞こえる声と、頭の中にある容姿のイメージとどうも一致しない。(どんなふうに違うのかと問われると言いにくいが・・・)
下山は十八曲がりの道を所々真っ直ぐに降りたためにかなり早く降りる事が出来た。もちろんヤマカカシの居た場所はしっかり記憶しておいて大きく迂回しました。
「記録」
登山口(09:02)---(.19)---(09:21)ヒカリゴケ洞窟---(.43)---(10:04)植林標柱(10:12)---(.05)---(10:17)稜線---(.09)---(10:26)山頂(13:20)---(.42)---(14:02)登山口
群馬山岳移動通信 /1993/