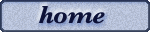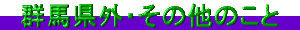快晴の登山日和を楽しむ「大平山(足尾)」 登山日2004年11月23日

| GPS軌跡データ |
| 山部薮人さんの記録へ | 松木川からのルートへ |
|
栃木の山を精力的に歩いている山部薮人さん、そしてその仲間のノラさんと一緒に歩いた。山部さんは2×4の角材を使って、特徴的な山頂標識を取り付けていることで知られている。その標識も栃木の山の全283座も、あと2座で完登という事であるという。そうすると、標識を付ける現場を見られるのもあとわずかということになる。そこで、どうしてもこの超人の行動を見ておきたいと思った。そこで同行をお願いしたところ、快く応じてもらうことが出来た。 11月23日(祝) 足尾の銅親水公園で待ち合わせる。外に出てスパッツを取り付けていると、私の車の横に高級外車が音もなく滑り込んできた。なにやら怪しい人物が出てくるのかと思ったら、山支度をした男性が二人降りてきた。そしてこちらに近づいてくる。おお、この人たちが栃木の山を自由に駆けめぐる人たちであろうか。背後から差し込む朝日がなんとも神々しくかんじられた。 「重鎮さんですか?」 「私は山部で、こちらはノラさんです」 そういって手をさしのべてきた。おおこの人が山部さんか感激しながら握手を交わした。 「よろしくお願いします」 山部さんは、体型的には私のコピーかと思われるほど、サイズが一致していた。(顔も似ているかもしれない)ノラさんはスリムで、山慣れている感じだ。相変わらず、バイクで遠方からこられて、山部宅に宿泊し、山部さんの車でこちらに来られたとの事だ。 3人で旧知の仲のように、並んで出発だ。なんだかんだと話が弾むが、インターネットの知り合いというのは不思議なものだ。無機質な機械がつなげた人間関係は、使い方によってはすばらしいものだ。以前、私が大平山に登ったときは、設置してなかったゲートが今は出来上がっている。ゲートは自動開閉で、許可車両だけが通過できるようになっている。カメラも設置してあるようで、その警戒ぶりは徹底していた。そんなゲートも人間が通過する分には全く問題ない。
やがて林道は分岐するが、地形図の様子から左に行ってみる。山蔭を回り込んでみると、どうやらこの道は行き止まりだ。さらに上部を見ると林道が走っているのがわかる。どうやら先ほどの分岐を右に行けば上部の林道に行けそうだ。衆議一決で戻って先ほどの分岐を右に行くことにした。 林道は順調に高度を上げていく。振り返ると透き通った大気の中に足尾の町が沈んで見えていた。また谷を挟んだ対岸の尾根は社山からのものであるが、その長い尾根はちょっと歩くには長すぎると思った。林道上の1151m標高点の分岐では、左にルートを取る。この林道は途中で切れてしまうように表現されている。ところが実際は林道は1356m標高点まで続いていた。
この標高点からいよいよ林道を離れることになる。尾根は明瞭で登るときは迷うこともなさそうだ。疎林の中の笹はそれほど深くなく、せいぜい膝程度である。踏み跡があるが、これはほとんどが鹿によって作られたののと考えられる。標高1600m付近で山部さんから声がかかった。どうやら、朝食抜きでここまで来ているとのことだった。こちらも願ったりかなったりで、ようやく休憩が出来るので喜んだ。
しばし、休憩後再び歩き出す。すると笹の中になにやら白いものがある。これは最近降った雪が残っていたものだ。今期初めての雪をすくってその感触を味わった。ささはちょっと深くなったが、それほど気になるものではなかった。 ところが突然右足のふくらはぎに激痛が走った。こむら返りだ!!しばらく痛みで動けない。しばらくジッとしていたらなんとか痛みが和らいだ。ヤレ、ヤレ、困ったものだ、こうなると再びこの痛みに襲われるのではないかと、恐怖心を持ってしまう。 疎林はさらに樹の本数が少なくなり、さらに快適になってきた。すると松木川から以前登ったときに見た風景が重なった。このあたりが合流点で、このコースでもっとも快適で展望の良い場所だった。ノラさんは先行している、山部さんはちょっとコースを外れて三者三様で思い思いに歩いた。それでも1805mの標高点には三人がほぼ同時に辿り着いた。 笹の原をノラさんを先頭に歩き出した。どうやらノラさんが一番元気なようだ。大平山へは尾根をこのまま辿って山頂の稜線に至り、ほぼ直角に右に曲がるのである。その直角に曲がる付近はちょっと笹が深い。嫌だなと思ったら、案の定今度は左足がこむら返りを起こしてしまった。先ほどの右足もまだ違和感がある。再び立ち止まって身動きが出来ない。数分間固まったままでジッとしていると、どうやら再び動くことが出来た。
笹原の上に身を投げて、大の字になって青空を仰いだ。実に気持ちがいい!!ビールを取り出して、一口呑むと実にいい感じだ。おまけにこの大展望はなにものにも替えられない。普段単独で行動しているものだから、三人での会話も実に楽しい。この休憩を利用してふくらはぎにテーピングを施して、顆粒のクエン酸を飲んでおいた。これでこむら返りの痛みは、すこし和らぐだろう。 40分近い休憩もあっという間だった。当初は社山経由で下山を考えていたが、時間もかなり遅くなっていることから、大平山の北東ひとつ目の1950m等高線に囲まれたピークから、南東に派生する尾根を下ることにした。  ザックを背負って歩き出す。1950mからの下降点は笹丈が深く、一部では胸のあたりまであった。しかし、下降と言うこともありさほど苦にならない。むしろ笹に隠れた倒木につまずかないようにするのに気をつかった。山部さんは倒木がある度に、「ここに注意してください」と知らせてくれた。何とも優しい人物であると感じた。しかし、そんな山部さんは転ぶときは豪快で、もんどり打って笹原を回転する。よくあれで怪我をしないものだと感心する。 この尾根は、人間は入らないのだろう。それらしい痕跡は見あたらない。唯一石祠のような石積みが1650m付近で見られたが、放置されてかなりの年月が経っているようだった。それだけに鹿の群れが多く、警戒の声を上げて尾根を走り回っていた。ノラさんが「鹿は倒木につまずかないのかな」と言った。なんとなく笑いが込み上げるようなつぶやきだった。 下降するに従って笹丈は低くなっていった。ここまで来ると心配は林道にどうやって下降するかと言うことだ。それは林道は削られて壁になっているからだ。1557mの三角点峰は西側を巻いて進んだ。その回り込んだところでとんでもない人工物に突き当たった。それは治山工事のために斜面をネットで覆いモルタルを吹き付けた、幅が数メートルに渡る部分が遮っていた。斜面の下は深い谷底になっていた。山部さんは何のためらいもなく、その斜面をトラバースして先に行ってしまった。ノラさんと私はその姿を唖然として見ていた。 私はどうしてもその数メートルの斜面を渡る気分にはなれない。斜面の上部を渡ることにした。しかし、上部は反対側がスパッと切れており、馬の背になっていた。これなら斜面の方がよかったかなと思ったがもう遅い。覚悟を決めてヒヤヒヤものでその馬の背を渡った。ノラさんは山部さんの渡った跡をそのまま渡った。  ヤレヤレと思ったが、ここで再び問題が発生した。尾根が分岐したのである。どちらも痩せ尾根で、下降するのは危なっかしい。右(西)の尾根の途中にはどうやら人の姿が見える。山部さんがヤッホーと声を掛けたが応答がない。しかし、その尾根は傾きかけた太陽を背に受けて、剣の刃のように見えた。左の尾根は、若干だが踏み跡が見られる。三人の考えはこの左の尾根を下降することで決まった。 この尾根も時々岩場に出くわして、窮地に陥ることもあるが、迂回すればなんとか通過出来るものばかりだった。1360m付近で尾根はちょっとだけ右(南)に曲がる。ここには植林のあとがあり、幼木の一本一本にネットがかけられていた。ここまで来れば安心、三人とも一様に安堵感に包まれた。それに道もハッキリしてきた、さらに鹿よけのフェンスには出入り口も取り付けてあった。 無事林道に出て、あとは三人で並んでこれからの山行について話しながら道を下った。いつしか目の前の赤倉山の上には上弦の月が白く浮かんでいた。 「記録」 07:44銅親水公園--(.13)--07:57阿世潟峠分岐--(.50)--08:47林道分岐左へ--(.09)--08:56堰堤引き返す--(.07)--09:03林道分岐右へ--(.17)--09:20林道分岐左へ--(.40)--10:00 1356m標高点10:05--(.30)--11:35 1805m標高点11:44--(.31)--12:15屈曲点--(.13)--12:28大平山12:42--(.11)--12:53休憩13:35--(.20)--13:55下降点--(.20)--14:15 1752m標高点--(.16)--14:31 1654m標高点--(.15)--14:46 1557m三角点--(.32)--15:18林道--(.22)--16:40銅親水公園 群馬山岳移動通信/2004 |