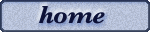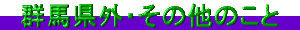峰の茶屋避難小屋も確認困難
|
那須岳は以前から登りたいと思っていたが、諸々の事情で後回しになっていた。その事情も無くなったようであり、年齢的にもこの辺が登りどきと考えた。何しろ那須といえば紅葉の名所でその時期に登ることはどうしても気が進まない。9月下旬ならば空いているだろうと出かけることにした。 9月26日(金) 午前4時半に自宅を出発、関越道、北関東道、東北道と乗り継いで行く。2日前には区長会の視察で通った道なのだが、全く記憶が無い。それだけ個人的には気合が入っていない区長会ということなのだろう。那須塩原ICで降りて峰の茶屋登山口に向かっていく。オフシーズンでもあり平日ということで渋滞もなく峰の茶屋の大駐車場に到着する。駐車場は半分ほど埋まっているが、ガラガラといったところだ。見れば麓は晴れているのに那須岳方面は雲に覆われており、時折雨粒が落ちてくるような天候だった。他の登山者も車の中から出て歩くのを躊躇しているようにも見える。さらに雨具を着ている登山者も見受けられる。 気分は落ち込みがちだが、3時間かけてここまで来たからには引き返す選択肢はない。車から外に出て出発することにする。石段を登り舗装路を歩いて行く。鳥居をくぐり山道を登っていく。程なく灌木帯を抜けて石ころの道となる。石は火山特有の赤茶けたものだ。時折硫黄の臭気がするが、気分的なものかもしれない。登山者はまばらで適度な距離を保っているのでストレスは感じない。それでも大声で話す団体はそれなりに耳に入ってくるのでうるさい。やがて眼の前に建物が見えてきた。到着するとこれが峰の茶屋避難小屋だとわかる。かつては営業茶屋だったのだが、今では避難小屋となっている。中には入らずに外で白湯を飲んで休憩した。 避難小屋からは雲の中を歩くものだから、周囲は真っ白で登山道の石だけが目に付く。登山道は石が累々と続き歩きにくい。やがて傾斜が緩やかになると、右に分岐する道が出てくる。これはお鉢巡りで一周したときの合流点なのだろう。しかし、展望がきかないものだからGPSで確認するしか無い。右の道には入らずに直進すると三角点の表示がある。茶臼岳の山頂取りも低いところにあるので見向きもされない不遇の三角点ということだろう。更に歩くと一気に賑やかな声が聞こえるようになり、鳥居と石祠がガスの中に見えた。山頂標識の前では記念撮影の順番待ちができていた。茶臼岳はロープウエイで来た場合30分程で到着できるのでそれなりの軽装の人が多い。賑やかな山頂でちょっとだけ休憩してお鉢巡りをしてから行くことにしたのだが、その道の標識が見当たらないので、しばらく迷ってしまった。
再び避難小屋に到着したが、ガスは相変わらず切れる様子はない。この付近は風の通り道なのだろう。風に恐怖を感じるほどで、眼の前の剣が峰は悪魔の棲む尖塔のように見えている。眼の前の剣ヶ峰は直登するのではなく周囲を回って迂回している。この道に入ると風は不思議と収まり、緊張は少しだが薄らいでいた。剣が峰と朝日岳の鞍部は岩のモニュメントが陳列されているような場所だった。ガスの中に自然が作った彫刻が浮かび上がっている様はあまり気持ちの良いものではない。中には絶妙なバランスで成り立っている岩もあり、いまにも崩落しそうな感じのものもあった。 道は更に険しくなり、岩場のトラバースが続くようになり、取り付けられた鎖につかまって歩く。足元は濡れており気を抜けばスリップして滑落は免れないだろう。いままで対向する登山者がいなかったのに、こんなところで3組の登山者とすれ違うことになった、かなり緊張しながら道を譲り合ってなんとか通過した。トラバースがすぎると今度はガレ場の斜面の登行となる。慎重に落石を引き起こさないように確実に登っていく。斜面を登りきると道が分岐する。ここは朝日の肩というところで、ここを起点にして朝日岳のピストンをする場所だ。休憩はせずに朝日岳を目指すことにする。
朝日の肩からひと登りすると朝日岳だった。晴れていれば大展望が広がっているはずなのだが、真っ白で何も見ることはできない。ほどなく到着した登山者と「最高の日を選んでしまいましたね」と愚痴を言い合った。山頂で菓子パンと白湯で栄養補給してから山頂を発った。 朝日の肩付近は風の通り道で風速は6メートル弱だった。ここからはなだらかな道が続き、熊見曽根という分岐を過ぎ、1900m峰をすぎると、一気に下降に転じ笹原の中を露に濡れながら下っていく。下りきったところが清水平で木道が設置されている。地形図からは湿原を想像するが、石を敷き詰めた場所に水が溜まっている雰囲気の場所が火山特有の雰囲気も見て取れるので、動植物は限られたものだけが定着するだけだろう。 清水平からは笹原の中の道を緩々と登っていく。時折現れるナナカマドの赤い実が秋を感じさせる。赤面山分岐までの道を登るとふたたび下降に転じるのだが、この道は泥濘がひどく足元は泥だらけとなってしまった。まるで田んぼの中を歩いているようなもので、この天候が余計に水分を補給しているようなものだ。下降が一段落して少し歩くと北温泉の分岐となるが刈払はされていないようで廃道に近い雰囲気だった。 北温泉分岐からは笹原の中の道を縫うように登っていく。ガスは相変わらずまとわりついて離れず息苦しくなるようでもある。メガネは水滴で曇って見えにくくなるので外してポケットにしまった。これだけで視界が明るくなりひらけたように感じる。やがて灌木も少なくなり、三本槍岳山頂に到着した。山頂は広い裸地となっており、三角点は埋没しておらず土の上に横たわっていた。かつて、甲子山から巣立山に登ったときに、もう少しで三本槍岳だと眺めた山頂にいると思うと感慨深い。山頂には数人のグループがいたので、離れた場所に陣取り昼食としたが、展望はなく休むと汗冷えがするのでゆっくりとはできなかった。
帰路は登ってきたルートを辿って駐車場に戻った。 長年、登るタイミングを見計らっていた那須岳は、あいにくの天候の中での山行となってしまった。しかし、ふたたび訪れることはないだろうと思う。 07:49峰の茶屋駐車場--(.49)--08:38峰の茶屋(避難小屋)08:46--(.36)--09:22茶臼岳09:36--(.31)--10:07峰の茶屋--(.45)--10:52朝日の肩--(.08)--11:00朝日岳11:21--(.37)--11:58清水平--(.40)--12:38三本槍岳13:03--(1.04)--14:12朝日の肩--(.32)--14:44峰の茶屋14:57--(.30)-- 15:27駐車 群馬山岳移動通信/2025 |