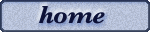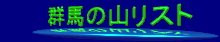登山日2025年1月7日

地蔵岳から見る大沼と黒檜山
|
1月7日(火) 赤城山の小滝は気になっていたのだが、なかなか出かける機会がなかった。正月の鈍った身体をほぐす為に出かけてみることにした。自宅をゆっくりと9時に出発した。前橋市街地を抜けて赤城山の道に入るが、雪はほとんどなく拍子抜けといったところだ。しかし、新坂平を過ぎて大沼への道に入ると風景は一変した。圧雪が続き、その表面は凍っているものだから、車が滑る様は半端ではなかった。しかし、ここで引き返すわけにはいかない。小沼への道はさらに状況が悪化し、傾斜のあるスケートリンクの上を走っているようなものだった。ハンドルは妙に軽く感じるので、帰路はかなりの困難を要することが想像できた。 駐車場は10台ほどが駐車していたが、ガラガラの状態といっていいだろう。支度を整えて出発だ。今回はスパイク長靴を選択したが、これは大正解だったようだ。まずは小沼の湖畔に降りたが小沼の凍結がどうも信用できないので、今回は小沼の横断はやめて外周を歩くことにした。10分ほど歩くとおおよそ半周したことになり水門に到着する。ここからわずかに歩くと分岐となるのだが、ここで行き詰ってしまった。小沼への道標なりがあると思っていたが、それらは皆無だった。しばらく悩んでいると、登山者が登ってきた。なんという幸運なのだろう。道を尋ねることにした。親切にご教授いただいて、進むべき方向がはっきりとした。それにしても何か案内があってもよかろうと思うが、冬季限定のものなので設置しないのだろうと勝手に想像した。
道は踏跡がしっかりとしており不安はなかった。しかし、ここでも案内標識がないのは意外だった。やがて深く切れ込んだ谷側の様子が分かってきた。さらに歩くと小滝とともに登山者の姿を確認することができた。この小滝への下降地点も標識がなく、踏み跡をたどりながら急斜面を下降するしかない。ところどころ積雪があり、気を許せない。幸いにもスパイク長靴がしっかりと効いているので不安感は全くない。小滝の氷瀑に到着する。氷瀑は気温が高いためか中程の部分が凍っておらず水が流れている。上部もまだまだ凍る部分があるのではないかと思われる。それにひっきりなしにツララが落ちて、カラカラと音を立てていた。しかし、これだけの規模の氷瀑を見られるだけでも満足しなければなるまい。氷瀑見物を10分ほどしてから、往路をたどって駐車場に戻った。
氷瀑見物だけで帰るのももったいないので、地蔵岳に登っておくことにする。地蔵岳に登ったのは30年ほど前になるだろうか。子供が小さいときに一緒に登ったことが思い出される。駐車場から八丁峠までの車道を歩き、ここから木製の階段を上ることになる。階段は微妙に雪がついており、いやらしい感じがする。ここでもスパイク長靴は最適で雪の上をすべることもなく歩くことができた。もしもアイゼンだったら木の部分に爪が食い込み登りづらかったに違いない。高度を上げるにしたがって小沼の全景が見えるようになる。また大沼も見えるようになると、大沼よりも小沼のほうが標高が高いのがわかる。この赤城山の沼の絶妙な配置は自然が作り出した妙というしかないだろう。やがて山頂近くになると雑木も少なくなり草原となってくる。最後の斜面を登りきるとそこには大展望が視野に入ってきた。あいにくと快晴ではないので青空を見ることはできなかった。目の前の最高峰である黒檜山は雨氷が残っており山頂部分が白く見えている。大沼の中心部には赤城神社の朱の部分が鮮やかに見える。しかし、この地蔵岳は無数のアンテナ群が何といっても目を引く。この無粋なアンテナ群がなければこの山頂はどんなにか素晴らしかっただろうと思いをはせる。山頂をひと巡りしてから駐車場への道を急いだ。
小沼駐車場10:41--(.11)--10:52水門--(.20)--11:12小滝11:23--(.26)--11:49水門--(.13)--12:02小沼駐車場 小沼駐車場--(.05)--12:22八丁峠--(.26)--12:48地蔵岳山頂13:09--(.15)--13:24八丁峠--(.03)--13:27小沼駐車場 群馬山岳移動通信/2025 |